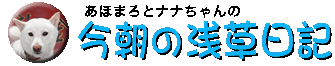
平成25年3月21日(木) 旧暦2月10日大安
|
今朝の撮影 Data Canon EOS 5D Mark III Canon EF24-105mm F4L IS USM Canon EF70-200mm F4L IS USM 現像 Adobe Photoshop Lightroom 4 撮影枚数748枚 |
- 骨董品にご注意を -

風が強くてとっても寒い朝になりました。昨日までは暖かかったので、今朝もジャンバーを着ないで散歩に出掛けてしまったおかげで、身体も冷え切ってしまったよ・・・。

今日は良いお天気になるようですが、これから日中にかけて風も寒さも続くようですね。せっかく咲いた桜も散ってましたよ。

予報によると、これから週末にかけて雲が多くスッキリとしない天気とか。そして日曜日にはニワカ雨の可能性もあるので、お花見は土曜日がオススメですって。酒を断ったあほまろには関係無いけどね。

アメリカのオークション大手サザビーズで、約1000年前の中国北宋時代に作られたお椀が222万5000ドル(約2億円)で落札されたようです。

北宋時代の同じ大きさ、形、装飾を施したものは、大英博物館が所蔵するもの以外確認されたのが始めてだったようですが、出品者は、近所のガレージセールで3ドル(約290円)で購入したとかで、ラッキーな方ですね。

このように欲が無くて買ったものが化けるのは嬉しいことだけど、テレビの「お宝鑑定団」を観ていると、骨董商から騙されて買わされた偽物の多いこと甚だしいよね。特に、バブル期に大枚はたいて買ったという品は全滅だね。

あほまろも骨董品を集めています。とはいっても、茶碗や絵画などでは無くて、昔のお金、それも四角い穴が明いた「古銭」ですよ。知らない人は、使えるお金を使えないお金に換えるバカな奴とか陰口を叩くこともあるけど、今だに買い続けているのよ。

金額的に幾ら使ったかは別として、穴銭、特に江戸時代の寛永通寳の鑑定にかけては日本でも有数の目利きと自負しているのですが、それでも過去に何度か騙されたこともありました。今ではそれも勉強だったと、諦めていますけどね。

たかが穴銭といえど、一枚数百万円の珍品だって存在するのです。あほまろが古銭に興味を持ったのは、祖父が古銭収集家だったことです。小学校の修学旅行で、札幌のデパートの古銭売り場で、どれでも10円の箱の中から祖父から伝授された知識を生かして拾い出した寛永通寳「小梅手銅銭」。帰ると祖父からおまえも目利きになったと褒められたことがあったよ。当時の相場でも10万円は下らなかったね。ちなみに現在の価格は30万円以上、もちろん今でも大切に持ってます。

小梅銭とは、江戸時代の小梅村で鋳造された寛永通寳です。墨田区(旧本所区)北部から旧向島区にかけての地域で、ちょうど東京スカイツリーの真下辺りが鋳造地だったんだよ。そんなことがきっかけで、古銭にのめり込むようになってしまったんだね。その後も、雑銭の中から価値ある古銭をいっぱい拾い挙げられたのも、偽物を掴まされなくなったのも、みんな祖父のおかげでしょうね。

先日、古銭商から送られて来たオークションに、寛永通寳「小梅手銅銭」が載ってました。下値が20万円と記されていたけど、どう見ても小梅手であっても別分類の「小梅手仰寛」だね。「小梅手」との違いは、「寳」の「貝」字の後爪が跳ねていないだけですが、これが一枚100円程度の雑銭になってしまうんだね。みなさんも骨董品を求める時には、くれぐれも気をつけましょうね。

ここ、↑ポチッと押してね。