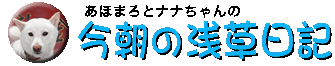
平成25年2月10日(日) 旧暦1月1日先勝 旧元日
|
今朝の撮影 Data Canon EOS 5D Mark III Canon EF24-105mm F4L IS USM Canon EF70-200mm F4L IS USM 現像 Adobe Photoshop Lightroom 4 撮影枚数718枚 |
- 新年快楽! -

あけましておめでとうございます。
今日は旧暦の元日です。日本ではお正月気分なんかすっかり抜けてしまいましたが、中華圏では盛り上がっているのでしょうね。

日本では、元旦から干支が変わるのが一般的になってしまったけど、本来は今日から干支が「巳」に変わるのですよ。

さっきNHKの天気予報で、「光の春」なんて耳慣れない言葉を使っていましたね。「光の春」を調べてみると、「小寒から大寒を経て節分にかけては一年で最も寒さの厳しい時期ですが、ひと足早く春に向かってもう歩み始めているものが日脚(ひあし)」、そんな意味の言葉なんだね。

二月の光は誰の目から見てももう確実に強まって、風は冷たくても晴れた日にはキラキラと光ことから、厳寒のシベリアでも軒の氷柱から最初の水滴の一雫が輝きながら落ちているという、ロシア語が語源の言葉のようですね。

ここ浅草でも、確実に春の兆しを感じるようになりましたよ。春になるとあちこちからくしゃみの音が聞こえて来るので、春の代名詞といえば、風流な「光の春」より、野暮な「花粉症」の方が春の代名詞みたいですよね。

今朝もとっても冷えていたけど、朝に集まるみなさんが、本堂前で、クシャン、クシャンと春をまき散らしてましたよ。

♪春は名のみの 風の寒さや・・・時にあらずと声も立てず・・・、そんな早春賦の歌詞ですが、現実は、
♪時にあらずと声も大きく、クシャン!クシャン!

毎年のことだけど この「早春賦」を思い出す季節になっても、東京は北風ビュービューで雪が降ったり、急に寒くなってしまうんだよね。これも人間が決めた「暦」と自然の巡りの誤差なんだね。日本も旧暦に戻した方が、古来からの季節感を肌で感じられるんだけどな・・・。

境内の梅もようやく開花しました。この梅が咲くと古来から「春」の代名詞になっていますが、日本土着の種ではなくて中国から移入されたものなのです。日本への渡来は、奈良時代の初頭とのことですね。

「春柳かづらに折りし梅の花誰か浮かべし酒盃の上に」の詩もありますが、この柳も同じころに中国から渡来した植物なんだって。梅も柳も完全に日本の風土に溶け込んでいるんだど、「暦」と自然の巡りまでが中国から渡来したってことなんだね・・・。

日中条約30周年の2008年、胡錦濤国家主席が初来日した時、暖かい春を迎えてと、現在の日中関係を表現していたことを思い出しますね・・・。

今朝も雲の流れが早く、朝日に照らされた雲がまるで水墨画のような描写を見せていました。

そういえば、水墨画も中国から伝わった表現方法なんだよね。これだけ深く残る中国文化。日中関係のこじれも春の到来を期待したいよな・・・。

---------------------------------------
お天気が良かったので、ナナちゃんを連れていつもの隅田公園でのんびり季節の影を追いかけてみました。





隅田川沿いのソメイヨシノの芽も膨らんできましたね。

触って見ると、かなり柔らかくなってましたよ。









白梅も開花してました。

写真に色は無いけど、暖かくなってきた季節を感じますね。



季節の影。











Memo
Leica M-Monochrome
Super-Elmar-M f3.8 18mm ASPH
SUMILUX-M f1.4/35mm ASPHERICAL
SUMILUX-M f1.4/50mm
Macro-Elmar 90mm f4.0
APO-TELYT-M 135 mm f/3.4
ここ、↑ポチッと押してね。