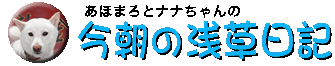
平成25年5月4日(土) 旧暦3月25日先負
|
今朝の撮影 Data Canon EOS 5D Mark III Canon EF24-105mm F4L IS USM Canon EF70-300mm F4-5.6 L IS USM 現像 Adobe Photoshop Lightroom 4 撮影枚数906枚 |
- 書を捨てよ、町へ出よう -

今朝も散歩の時間は寒かったのでジャンバーを着込んで出掛けたのですが、陽が昇ると春の陽気でしたね。

今日は、新緑がまぶしいみどりの日ですからね。これから入梅までが、あほまろとナナちゃんの一番好きな季節になるのです。

梅雨が始まると、ナナちゃんの抜け毛の季節。はっきり言って来て欲しくないんだよな・・・。

今年は、寺山修司没後30年の節目の年。渋谷区道玄坂二のポスターハリスギャラリーで「寺山修司と天井桟敷 全ポスター展」が開催されています。

寺山修司が主宰した劇団「天井桟敷」のアングラ演劇、あほまろの青春そのものだったね。それと、「書を捨てよ、町へ出よう」カルメン・マキ「時には母のない子のように」等々、懐かしさが蘇ってくるようでした。

「書を捨てよ町へ出よう」は、間違いなく影響を受けた一冊だったよ。自殺学入門で自殺はしたくなかったけど、思い出すのは、お金が無いので、せっかく集めた切手や古銭を全部売っぱらって家出しよう。そんなことを真剣に考えたことがあったね。

よ〜し、実行しよう。切手のストックブック三冊をカバンに詰め、新宿駅ビルの切手商に売りに行ったね。ところがギッチョン、当時の記念切手は総て額面の半額以下だと言われ、売るのを断念してしまったよ。

今も、その時のストックブックを持っていますよ。見るたびにあのときの事を思い出すたびに、「青年よ大尻を抱け」と、吹いてしまう。

「あなたも不良になれる」、そんな志を持って人生を歩んで来たんだけどな・・・。振り返ってみると、今のあほまろ体調不良に苦しんでいるだけ。だから今日から禁酒をする覚悟なのさ。

「書を捨てよ、町へでよう」。と言われても、捨てないで持ってるよ。あほまろ、今でも落ち込んだ時(いつも落ち込んでいるけど)に開く一冊になっているんだね。これだけは、電子書籍では存在感が薄れて物足りなくなる、いわゆる「本」なのだよ。

「本」という漢字は、「物事の基本にあたる」という意味から転じて書物を指すようになった言葉なのですから。

あほまろの学生時代(1960年代〜1970年代)は、アングラ演劇が勢いを持ち、寺山修司(天井棧敷)、唐十郎(状況劇場)、鈴木忠志(早稲田小劇場)、佐藤信(黒テント)、串田和美(自由劇場)等々。

当時は現実離れした心地よい「嘘」の世界、異質な世界観があったんだけど、現代演劇ではそれが当たり前の世界になってしまいましたね。

ごく当たり前に「嘘」を堂々とさらけ出す演出は、アングラ演劇が完成期に入った証拠なのでしょうね。

それで、実験的な芸術パフォーマンスの土壌を切り拓いてきた人物としての寺山修司は、絶対的な存在として現代にも名が受け継がれているのです。

アングラ演劇の創業者の一人である、状況劇場の唐十郎は今も健在ですよ。そういえば、仲が悪かった天井桟敷と状況劇場なのに、どっちも横尾忠則がポスターを制作していたのも不思議なことですね。

それが理解に苦しむ、常識を飛び越えたアングラの世界だったのかも。あほまろ、今でもアングラ 文化を邁進するような孤高の生き方を楽しんでいるのでしょう、たぶんだけど・・・。

ここ、↑ポチッと押してね。