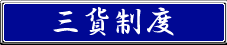
○三貨制度 こでは、江戸時代の三貨制度について簡単に述べるに留める。 江戸時代のお金の単位は非常に複雑な構造になっている。
まず、三貨制度とはお金の素材が「金」「銀」「銅」の三種類で 制作されていた。そんな素材の貨幣は世界も同じ、ただ江戸では、 この三貨がそれぞれ独立していて、換算率が一定ではなく、たえ ず変動していたのである。
公的には金一両=銀五十匁(元禄以降は六十匁)=銭四千文 と、定められてはいたのだが、実際は民間の両替商の相場で変 動し、幕府財政難の時は小判等の金の含有率を下げるると、たち まち市場相場に跳ね返って来る微妙な換算率で動いていた。
江戸の通貨
金(小判) =一両(りょう)=四分(ぶ)=十六朱(しゅ)
一分(ぶ)=四朱(しゅ)=銭千文 一朱(しゅ)=銭二百五十文 銀=金一両=銀六十匁(もんめ)
相場の変動
寛永二年公定 六十匁
天明〜寛政 五十七匁〜五十八匁
享和〜天保 六十二匁〜六十六匁
元治〜明治 百五十匁前後
銭=金一両=四貫(かん)文 注:四貫文は銭四千文
と、定められていた。(詳細図版は制作中)
俗に、「関東の金遣い」「上方の銀遣い」といわれるように、 商人の取り引きでは東国(関東)では主に金が、西国(関西)で は主に銀がが使われ、身分制度によっても使用する貨幣が違い、 上級武士は金貨、下級武士と商人は銀貨、庶民・農民は銭貨と分 かれていた。勿論庶民でも金貨銀貨を使用できるが、両替商に庶 民が金貨(小判)等を持ち込むと、帳面にその入手経過を詳しく 調査され、お上に届け出なければならなかった。
