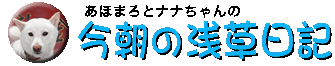
平成22年1月22日(金)
- 元の木阿弥 -

昨日の春のような暖かさが一転し、今朝は冬の寒さに戻ってしまいました。寒いのなんのって、シャッターを押す指の感覚も全く無くなってしまうほどでしたよ。
おかげで、空気が澄んで富士山が綺麗に見えていましたけどね。

寒そうだね・・・。出かける前のナナちゃんの不安な表情。

やっぱり今朝は寒かったよ・・・。散歩から帰って来たエレベータの中で、まだ震えてましたよ。

今日は、浅草で江戸時代幕末から明治にかけて活躍した歌舞伎狂言作者河竹黙阿弥の命日です。彼の居住地跡碑が現在の仲見世会館前にありますが、実際はもっと東南の馬道に面していたのです。それは、古地図で確認できますけど、距離にして僅か百メートルほどは誤差として許されるのでしょう。
浅草伝法院通り東側商店街には、彼の代表作、「知らざあ言って聞かせやしょう」の名台詞で知られる歌舞伎の「青砥稿花紅彩画(通称:白浪五人男)」を模した人形が飾られています。歌舞伎を知らない人でも、河竹黙阿弥流の台詞はどこかで耳にしてお馴染みでしょう。これらの五人男、お芝居のように一筋縄には探せません、みなさん意外な場所で通行人を見ているのでからね。永きにわたり江戸っ子をとりこにしてきた黙阿弥調の小気味よい台詞の名調子をつぶやきながら、天下の盗人五人組を捜してみるのも、浅草観光の楽みとなっているのです。
また白波五人男以外にも、西側商店街の軒先に掲げた木製看板や飾りなどが江戸の舞台も演出していますよ。そんな中でも、やはり江戸っ子の洒落といえば、地口行灯(じぐちあんどん)ですね。諺や成句の言葉をもじって遊ぶことで、お稲荷さんの初午の縁日に飾ることでもお馴染みの行灯、それが年中、伝法院通りを飾っているのですよ。
木阿弥といえば、「元の木阿弥」。いったん良い状態になったものが、再びもとのつまらないさまにかえること。苦心や努力も水泡に帰して、もとの状態にもどってしまうことを表す言葉ですが、河竹木阿弥から派生した言葉ではありません。戦国の世に、大和の武将筒井順昭が不治の病で亡くなり、まだ幼い息子に乗じて、お家騒動の恐れを回避しようと、声がよく似ている奈良の木阿弥という貧乏な僧侶を影武者に仕立て、やがてお家騒動も収まり、贅沢な生活の任が解かれ、渋々奈良に戻っていったことから、「元の木阿弥」と言われるようになったとか。
あほまろのように、常日頃、禁酒を心得ながらもついつい飲んでしまうのを、本当に止めてしまったら・・・、「元の木阿弥」といえるのかな。
『最近のアルバム』
● 第21回東京時代まつり
● 浅草奥山阿波おどり
● 第一回浅草阿波おどり
● 目黒碑文谷八幡宮秋期例大祭
● 第29回 浅草サンバカーニバル
● 浅草寺の不思議空間・パワースポット